デジタルトランスフォーメーション(DX)という言葉が日本で浸透するきっかけとなったのは、経済産業省が2018年に公表したDXレポートでした。レポートが公開された当初、「IT機器のレガシーをリプレイスする」ことがDXであると誤認されていました。
それから約7年。DXレポートの更改版などの公表もあり、DXが「IT技術の活用による企業文化・ビジネスや社会の変革」と定義されていることは、広く認知されています。
そうした中、これまで多くの中小企業のDXを支援してきたAI・IoT普及推進協会(AI・IoT Promotions Association/通称:AIPA)・代表理事 兼 事務局長の阿部満氏は「その考え方では遅い」と指摘します。
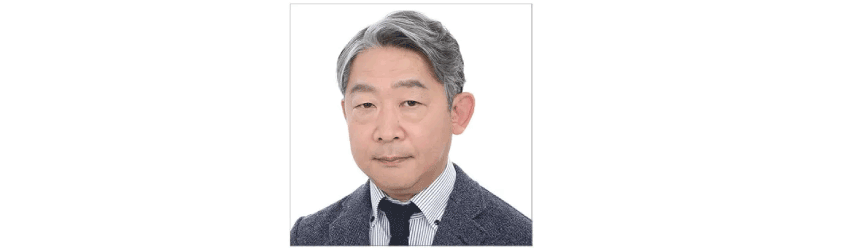
阿部氏によれば、「これからのDXにはITだけでは不十分で、AIが必須となる」とのこと。AIがDXの鍵を握っているのはなぜなのか、中小企業においてAI活用を進めるコツとは、AIを軸にDXを進めていくために中小企業が持つべきマインドセットは、etc.――AIPAの阿部氏にお話を伺いました。
DXにAIは必須。2019年から見据えていた未来像
――まず、AI・IoT普及推進協会は、どのような活動をされているのですか?
AI・IoTコンサルタント(AIC)を育成・認定し、現場で実際に指導できる仕組みを構築するのが事業の柱です。DXの課題を抱える中小企業とAICの橋渡しを行い、中小企業におけるDXの促進を支援しています。
AICの仕事は、経営層や現場の課題、業務フローをヒアリングしながら、適材適所にAIやIoTを導入するお手伝いをすることです。導入から運用まで、伴走して支援しています。
――なぜこのような活動をされているのですか?
現代日本の中小企業における最大の課題は人不足です。年間で約50万人も人口が減少しており、鳥取県や島根県の人口と同じくらいの人が毎年消失し続けています。そうした環境下で事業を継続するには、人の仕事を代替してくれる存在が必要です。それがAIというわけですね。
ですが、中小企業へのAI導入を支援できる人材は不足しているのが実情です。世の経営コンサルタントや本来は専門のはずのITコンサルタントの方でも、AIに精通しているという方は多くありません。その穴を埋めるため、当協会ではAICを育成しています。
――協会の設立は2019年ですが、その当時から「AI」を名称に掲げられた理由は何でしょうか?
設立当初から、AIはIoTと切り離せないものだと考えていたからです。ITツールを使えばデータベースを作成・管理することはできますが、それを分析して活用していくにはAIの力が必要になります。
DXの中核は、データドリブンです。デジタルのDはデータのD。DXは「データトランスフォーメーション」といっても過言ではないと考えています。それを可能にするのがAIなのです。
――早期からDXの本質をとらえていたわけですね。
AI・IoT普及推進協会という名称の由来は、協会の設立前、政府によって策定された「Society 5.0」の概念に基づくものでもありました。現在では、この名称にしておいてよかったと考えています。
中小企業に蔓延する「DX疲れ」とは
――中小企業でDXを進めるにあたっての課題はどのようなところにありますか?
そもそも「DXにAIは不可欠」という認識のある人が少ないことです。この結果として、「DX疲れ」という現象が増えています。DXをITだけで対応したせいで望んだ効果が出ず、疲弊してしまうのです。ITツールを導入したのに人間の作業工数が減らない現状に嫌気が差し、DXという言葉を敬遠する経営者もいます。
私自身の体験をお話ししますと、以前、長野県でのDXに関する講演に呼ばれたことがありました。ですが人が集まらないのです。その講演を主催した組織は、DX関連の講演をたくさんやっていたのですが、みんなITの話ばかり。
ITだけでは効果が出ないから参加しても意味がないと、だれも来なくなってしまいました。DXはAIを使ってこそ効果が出ます。だから、まずはDX=ITという認識を改めなくてはいけません。
そして、AIの活用という面では、AIに何をどうやらせればいいのか分からないというケースが多いですね。ITツールであれば、会計や人事、生産管理といった具合に、やれることが明確化されています。ですが、AIはある程度なんでもできてしまう。AIに何をどうやらせれば業務効率化につながるのか、選択肢が多すぎて分からなくなってしまうんですね。
――確かにITツールは、どこに導入すべきソリューションか明確ですが、AIはそういうわけには行きません。それを解決するにはどういった取り組みが必要ですか?
大前提として、「AIには何でも任せられる」というような夢を考えるのではなく、AIでできる課題解決を探すことです。私が中小企業を支援する際には、まずは社長から現場まで幅広くヒアリングをして、何に悩んでいるのか分析します。そして課題を見つけて、解決策を提示します。単に「AIを導入する」のではなくて、「AIで課題を解決する」という話に持っていくのです。
そのうえで顧客にソリューションを提案する際は、導入費用を抑えるため、可能な限り既存のツールを提案します。今はたくさんのAIツールが開発されていますから、選択肢は豊富です。必要に応じて、ベンダーによるカスタマイズや開発を行うこともあります。
――具体的な事例を教えてください。
ある製造業の会社を支援したときのお話です。その会社では、多ければ1日に100件も見積依頼が来ます。その依頼に対して、社長が一つひとつ自分の感覚と経験をもとに判断し、見積書を作成していました。そのため社長は見積もり作成のタスクに追われ、社長としての他の仕事に手が回らずにいました。
そこでAIに、工場の図面や工数のデータ、使う機械の情報、過去の事例、原価計算のロジックを与え、見積もり作成の仕事を任せることにしました。すると、社長は自らがやるべき仕事に集中できるようになっただけでなく、処理できる見積もりの作成数が大幅に増えたんですね。
見積もりを出せる数が増えれば、当然受注も増えます。ツールの導入には200~300万円のコストがかかりましたが、それを十分に回収できるだけの受注増を獲得できました。
この事例のように、業務におけるボトルネックを発見し、ピンポイントで課題を解決していくのが重要です。適切な課題解決ができれば、1カ所を変えるだけでも非常に大きな効果を得られます。
これからAIを導入する中小企業に必要なこと
――これからAIを導入したい中小企業は、どのようなことから始めればよいでしょうか?
最初にやるべきこととして、社内で人を育てることが重要です。若手に、AIを使うチャンスを与えましょう。トップダウンでAIを使うように命令する。そして、失敗を許すことが必要です。
初めのうちは、ChatGPTなどの生成AIを使えばいいと思います。これなら、ローコストで導入できますからね。ChatGPTもバージョンアップが進んで人間らしさが向上しているので、色々なものを作れます。営業の日報を生成AIに作ってもらうだけでもだいぶ楽になるでしょう。企画職なら、製品のキャッチコピーなどを考えてもらうのもいいですね。生成AIを使いながら、経験値をどんどん積んでいきましょう。
また、従業員に対して、AIを活用したことでメリットを得られる仕組みづくりも大切です。AIの効果で業務時間が短縮されても給料を維持する、余暇を増やすなど、業務効率化による恩恵を与えましょう。そうすれば、積極的にAIを使おうという土壌が出来上がります。
ここで大切なのは、AIは道具であると認識し、全部を任せないことです。AIに作業を任せたとしても、最後のチェックは人の手と目でファクトチェックを行ってください。あくまでも主役は人であり、人がAIをマネジメントするのです。
企業の本質は“現場”にある
――AIの導入が進むと、ビジネスはどう変わっていくと思いますか?
AIにより何が起きるかといえば、事務作業が効率化されてオフィスワーカーが減ると考えています。そして、オフィスワーカーが減ったぶん、現場に人を回せるようになります。
事務系の仕事の多くをAIにより代替できますが、現場は人がいないと動きません。私は、企業の本質は“現場”にあると考えています。それゆえ、オフィスワークはどんどんAIに任せて、現場により多くの人を割り当てていくべきなのです。
世に出ている「ITツール」は、ほとんどがオフィスワーカー向けで、現場とは関係ありません。ですが、AIによるDXに成功して「うちの会社の強みは現場にある」ということに気付く経営者が増えるのではないでしょうか。
| ここがポイント! |
| ●DXの中核はデータドリブンによるビジネス変革にあり、これを実現し得るのがAI。 |
| ●従来のITツールだけでDXを進めようとしたことで、「DX疲れ」が蔓延。 |
| ●AIの導入では、まず社内でAI人材を育てることが重要で、そのための仕組み作りが必要。 |
| ●企業のビジネスの本質は“現場”にある。現場力を強化するためにAIによるオフィスワークの効率化が不可欠。 |
外部リンク
一般社団法人AI・IoT普及推進協会(AIPA)


無料会員のメリット
- Merit 1 -
企業向けIT活用事例情報のPDFデータをダウンロードし放題!
- Merit 2 -
本サイト「中小企業×DX」をはじめ、BCNのWEBメディア(「週刊BCN+」「BCN+R」など)の会員限定記事が読み放題!
- Merit 3 -
メールマガジンを毎日配信(土日祝を除く)※設定で変更可能
- Merit 4 -
イベント・セミナー情報の告知が可能!自社イベント・セミナーを無料でPRできる
- Merit 5 -
企業向けIT製品の活用事例の掲載が可能!自社製品の活用事例を無料でPRできる

無料会員登録で自社製品の事例をPR!
企業向けIT製品の活用(導入)事例情報を無料で登録可能!
新規で会員登録される方は会員登録ページ、(すでに会員の方は、会員情報変更ページ)より、会員登録フォーム内の「ITベンダー登録」欄で「申請する」にチェックを入れてください。
未会員の方はこちら



