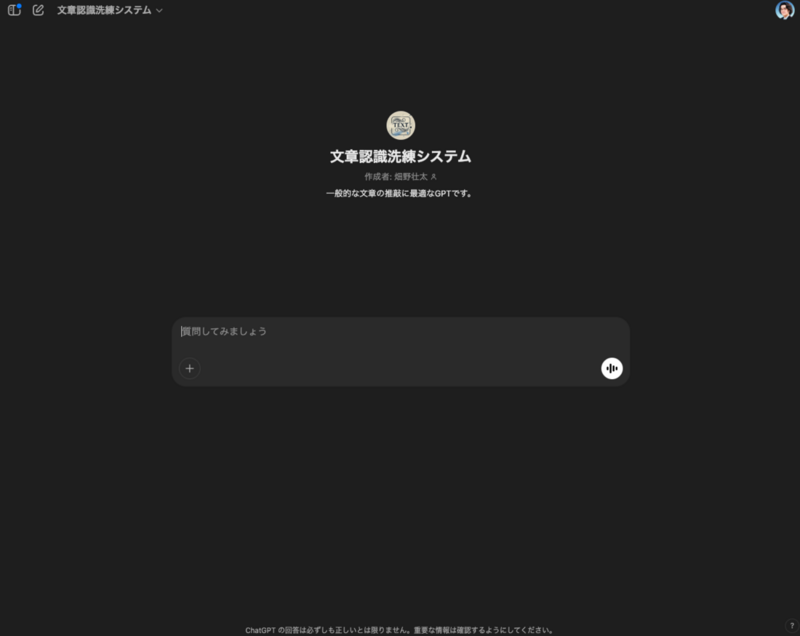毎回、長文のプロンプトを打ち込むのが面倒だ――生成AIを使っていて、このように感じている方は多いのではないでしょうか。
生成AIを使いこなすうえでプロンプト(指示)は最も重要な要素ですが、望み通りの成果物を得るには、詳細な指示が必要です。それゆえ、プロンプトの作成は手間であり、その入力作業の効率化は無視できないものでしょう。
実は、プロンプト入力の手間は軽減できるのです。それは、“生成AIをカスタマイズする”こと。カスタマイズにより、プロンプトを毎回入力する手間から解放され、成果物の精度も向上させることができます。
今回の連載では、ChatGPTの「GPTs(ジーティーピーズ)」を例に生成AIのカスタマイズについて全5回で解説します。
第1回となる本稿のテーマは、生成AIをカスタマイズすることによって得られるメリットについてです。カスタマイズによって何がどう変わるのか、まずは概要を理解していきましょう。
※本稿は、2025年3月時点の情報にもとづき執筆しています。
生成AIをカスタマイズするメリット
生成AIをカスタマイズすることによって得られるメリットは、大きく2つあります。「毎回、プロンプトを打ち込まなくてもよくなること」と、「成果物の精度向上が期待できること」です。
メリット1:毎回、プロンプトを打ち込まなくてもよくなる
生成AIのカスタマイズによる最も大きなメリットといえば、「プロンプトを打ち込む手間が大きく軽減される」ことです。これを実感いただくには、以下のようなビジネスシーンをイメージするとよいでしょう。
例えば、会社の新規事業を策定する際に生成AIを活用する場合、どのようなプロンプトが必要になるでしょうか。事業概要や経営状況、強みや弱みなど、会社の情報だけでも多くの項目を生成AIに伝えねばなりません。さらに、市場の状況や他社の動向といった情報も必要になります。また、企画を通すことを考えれば、上長や役員など社内上層部の人の性格も、情報として知っておいてほしいところです。
上記だけでもかなりの量になりそうですが、これらはプロンプトにおける前提情報に過ぎません。ここまでの情報を与えたうえで、新規事業の内容について対話していくことになります。
前提情報まで網羅したプロンプトを書いていたら、かなりの手間がかかってしまうのは確実です。それに、新規事業のための企画は一度やって終わりというわけではありません。ヒットする優れた企画を策定するには、数多くの企画を考えることが必要でしょう。
とはいえ、大量の情報を生成AIに毎回伝えるのは面倒。そこで、カスタマイズの出番です。生成AIをカスタマイズすることにより、知っておいてほしい情報を事前に伝えてておくことができます。上記の例では、膨大な前提情報を毎回教える必要がなくなるわけです。
カスタマイズした生成AIは後からでも編集できるので、市場の状況など情報に変化があった場合は、その部分を修正すればよいだけです。つまり、プロンプトのアップデートも簡単といえます。
メリット2:成果物の精度向上が期待できる
特定の作業をする場合、素人よりも慣れている人の方が質の高い作業を行えることはいうまでもありません。生成AIでも、それは同じです。カスタマイズされた生成AIは、必然的に特定の作業に特化したものになりますから、成果物の精度向上が期待できます。
例えば、自社のプレスリリース執筆専門の生成AIを考えてみましょう。この生成AIをカスタマイズする過程では、文体や文字数、見出しの付け方などをプロンプトで指定しておくことになります。さらに、過去に公開したプレスリリースのデータを学習(*1)させることも可能です。
(*1)人間の思考や判断をコンピュータで模倣するために、経験や知識を蓄積して判断の精度を上げること
これだけの情報をカスタマイズにより事前に与えておくことで、ある程度その作業に“慣れた”状態を作れます。
ここまで、生成AIをカスタマイズするメリットを理解いただけたのではないでしょうか。端的にいえば、「時短」と「精度向上」の一石二鳥の効果が得られます。生成AIで同じ作業を繰り返す場合などには、かなり重宝しそうです。
ChatGPTのカスタマイズ機能「GPTs」
生成AIには、さまざまなツールがあります。今ではカスタマイズ機能を搭載したツールも増えていますが、その先駆けはChatGPTが備えた「GPTs(*2)」です。現時点で、ChatGPTは世界で最も多くのユーザーを抱える生成AIであり、GPTsはその人気を支える重要な要素のひとつともなっています。
(*2)現在、ChatGPTではGTPsの表記は「マイGPT」に変更されたが、一般的にはGPTsと呼ばれている。本連載では一般表記としてGTPs、機能や操作説明においてはマイGTPを使用
そこで、本連載ではChatGPTのカスタマイズ機能であるGPTsを例に、生成AIをカスタマイズする方法を解説していくことにします。
GPTsとは、前述したようにChatGPTをカスタマイズできる機能です。プログラミングなどのスキルがなくとも、自然言語を入力するだけで「文章推敲用GPT」といった特定業務に特化したオリジナルの生成AIを作成できます。いわば、生成AIをノーコード開発するイメージでしょう。
開発したオリジナルのGPTは、組織内で共有したり、一般に公開したり、逆に公開されているオリジナルGPTを利用したりできます。開発したGPTを公開して課金する仕組みも検討されており、将来的には収益化も期待されています(*3)。また、プログラミングの知識は必要ですが、API(*4)を介して外部サービスと連携させることも可能です。
(*3)2023年に方向性として発表されたが、現時点では実現されていない
(*4)Application Programming Interface:ソフトウェアやWebサービスなどのプログラムをつなぐインターフェイス
こうした特徴を鑑みれば、GPTsを理解してうまく活用することでビジネスを飛躍的に効率化させることも期待できるわけです。
「GPTs」を使うには
カスタマイズ機能であるGPTsを使用するには、ChatGPTの有料プランを契約する必要があります。有料プランには、個人向けの「Plus」「Pro」の他に、組織用の「Team」「Enterprise」の全4種類が用意されています。
どのプランでもGPTsを利用できますが、比較的コストパフォーマンスのよい「Plus(月額で税別20ドル)」が基本的にはお勧めです。というのも、「Pro」は主にプログラマーや動画制作者に向けたプランで、動画生成AIなどを無制限に利用できるといったメリットはありますが、月額で税別200ドルと高額であることです。
企業での使用を検討するなら、「Team」や「Enterprise」も選択肢とはなります。「Team」は性能面ではPlusとほぼ同等ながら、コラボレーションといった組織に必要な機能や法人・組織向けのサポートなどが付随するため、コストが1人当たり月額で税別25ドルとやや高めに設定されています。実証実験など少人数で利用する場合には割高となるだけに、一定以上の人数で使いたいなど利用環境を考慮して検討した方がいいでしょう。
なお、「Enterprise」については大企業専用のプランで、価格も要問い合わせというもの。契約のハードルは低くありません。
こうした理由から、編集部ではChatGPT Plusを契約して検証を行なっています。今後の本連載で掲載するGPTsの操作や成果物は、このプランによるものとなります。
次回は、GPTsの概要や操作方法などを解説していきます。どれほどの時短や精度向上が見込めるのか、実例を交えながら見ていきましょう。
| ここがポイント! |
| ●生成AIのカスタマイズにより長いプロンプトを入力する手間を軽減。 |
| ●カスタマイズされた生成AIは特定の作業に特化したものとなり、精度の向上が期待できる。 |
| ●ChatGPTのカスタマイズ機能「GPTs」を用いて、オリジナルGPTを簡単に開発することが可能となる。 |
| ●「GPTs」を利用するには有料プランの契約が必要。 |


無料会員のメリット
- Merit 1 -
企業向けIT活用事例情報のPDFデータをダウンロードし放題!
- Merit 2 -
本サイト「中小企業×DX」をはじめ、BCNのWEBメディア(「週刊BCN+」「BCN+R」など)の会員限定記事が読み放題!
- Merit 3 -
メールマガジンを毎日配信(土日祝を除く)※設定で変更可能
- Merit 4 -
イベント・セミナー情報の告知が可能!自社イベント・セミナーを無料でPRできる
- Merit 5 -
企業向けIT製品の活用事例の掲載が可能!自社製品の活用事例を無料でPRできる

無料会員登録で自社製品の事例をPR!
企業向けIT製品の活用(導入)事例情報を無料で登録可能!
新規で会員登録される方は会員登録ページ、(すでに会員の方は、会員情報変更ページ)より、会員登録フォーム内の「ITベンダー登録」欄で「申請する」にチェックを入れてください。
未会員の方はこちら